- 実施事例
- パラリンピックメダリストによる講演会とデモンストレーション
講演会事例 パラリンピックメダリストによる講演会とデモンストレーション
- 主催者
- 中央区立佃中学校
- 講師
- 菅野浩二選手(車いすテニス)

- 開催日
-
- 2025.02.15(土)
- 場所
-
- 佃中学校 体育館
- 対象
-
- 佃中学校の全校生徒ならびに保護者
- 参加人数
-
- 約330名
覚悟を持って挑戦することで夢は実現する

車いすテニスのプロ選手として、世界中をツアーで回っている菅野選手。東京2020パラリンピックにも出場し、銅メダルも獲得しています。まずは、「夢舞台への挑戦」との講演を行いました。
菅野選手は高校1年生のときのバイク事故により、首から下の身体機能に障害が残り、車いす生活を余儀なくされます。当初、握力は55kgから3kgとなり、「医師からこの先一生車いすだと説明を受けたときは1日中ベッドで泣いていました」と、振り返ります。
しかし、学校の先生からの励ましなどにより徐々に元気を取り戻し、半年ほど経った後にリハビリ専門の病院に移ります。そこでパラスポーツに取り組む仲間や、車いすテニスと出会います。ただ「当時はあくまで趣味でしたね」と言います。
ところが、東京2020パラリンピックの開催が決定したことで、「出場したい」との夢を抱きます。勤めていた会社の「アスリート制度」を活用し、週の半分を練習に充てました。
さらには、年ごとの目標を明確に掲げると共に、一歩ずつ前進していきました。まずは日本ランキングで1位になること。3年目はウィンブルドンなどのグランドスラム大会への出場。4年目は東京2020パラリンピックへの出場ならびに、メダル獲得です。そして見事、すべての目標を達成します。
菅野さんは最後に、次のようなメッセージを送りました。
「人生では一度くらい、大きな勝負をする必要があるのではないでしょうか。覚悟を持って挑戦すれば、無理だと諦めていたことができるかもしれない。そのように思っています」

菅野選手より「僕も新たな挑戦に臨みます!」


講演をしっかりと聞いてくれたので、進行しやすかったです。ラリーでは生徒さんがとても上手だったので、厳しいボールなどもあり、実は内心では「やばい」と思っていました(苦笑)。
本来、僕は人前で話すことは得意ではありません。でも、今日のようなイベントをきっかけに、僕のような人生を送っている人がいることを知ってもらえるし、障害者スポーツに興味を持ってもらえる人が増え、実際にボランティアなどに参加してくれる人も少なくないので、活動を続けています。
近々20年近く働いていた会社を辞め、フリーランスになります。プロテニスプレーヤーとしての活動と、講演会などの活動、さらには書籍の執筆や映画製作など、やりたいことがたくさんあるからです。僕もチャレンジを続けていきます。
主催者(中学校)より「困難に直面したとき、今日のことを思い出してほしい」

道徳や総合的な学習の授業で、積極的に講師を招き、話を聞くなど、体験的な学習を行っています。今回は、事故で車いす生活になりながらも、強い意志をもってパラスポーツ選手として活躍する選手について学習したいと考えました。
そこで、実際にパラスポーツを見たり、体験したりしてもらいたいと考えていたところ、東京パラくるの存在を知り、東京都が運営している信頼感もありお願いしました。
パラリンピックを詳しく知らない生徒や、間近でパラリンピック選手のプレーを見るのは初めての生徒も多いので、みな興味津々の表情を見せていたのが印象的でした。
生徒たちはこの先、思うようにいかないことがあるかもしれません。そのようなとき、今日の講演内容や菅野選手のことを思い出し、新たな目標を持つなどして乗り越えてほしいと思います。
-
戻る









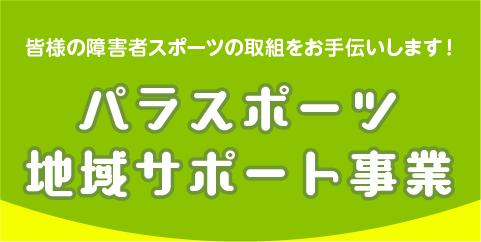




高校生になったら、菅野さんのように大きな挑戦をしたい
講演の後は、ソフトテニス部の生徒が菅野選手に車いすの乗り方を教わり、全生徒や保護者に注目されるなか、ラリーによるデモンストレーションを行いました。さすがはテニス部員。車いすの扱いには苦労していましたが、時折エースを決めます。
菅野選手も厳しいボールを打ち返すなどのパフォーマンスを見せると、生徒たちからは「おーっ!」との歓声が上がっていました。
ラリーに参加した生徒からは、「テレビで観ていて車いすテニスはフットワークが難しいと思っていましたが、まさにその通りでした。打つことに集中してしまい、車いすを動かすことがまったくできていませんでした」との感想が聞かれました。
別の生徒からも「上半身と下半身を同時並行で動かすことが難しかったです。外から見ていると選手は簡単そうにやっているので、すごいと思いました」との感想を述べました。
生徒には講演会の感想も聞きました。
「パラリンピックメダリスト本人から直接、実体験や思いを聞くことができ貴重な機会でした。特に最後のメッセージは印象的で、私も高校生になったら生徒会長になる。そのような大きな挑戦をしてみようと思いました」