- 実施事例
- デフバドミントン矢ケ部紋可選手、学生に伝えた聴覚障害者のスポーツと食の工夫
講演会事例 デフバドミントン矢ケ部紋可選手、学生に伝えた聴覚障害者のスポーツと食の工夫
- 主催者
- 中野区、新渡戸文化短期大学
- 講師
- 矢ケ部 紋可選手(デフバドミントン)

- 開催日
-
- 2025.09.03(水)
- 場所
-
- 新渡戸文化短期大学 東高円寺キャンパス NITOBE Happiness Hall
- 対象
-
- フードデザイン学科の学生、教職員、地域住民
- 参加人数
-
- 58名
東京2025デフリンピック目前、矢ケ部紋可選手が講演

東京で初めて開催されるデフリンピックを前に、デフバドミントン日本代表の矢ケ部紋可選手が、新渡戸文化短期大学で講演を行いました。会場にはフードデザイン学科の学生を中心とした多くの参加者が集まり、聴覚障害とスポーツの関わり、食事管理、そしてデフリンピックの魅力について熱心に耳を傾けました。

東京2025デフリンピックを一緒に盛り上げたい!

講演会で感じたのは、デフリンピックの認知度はまだまだ広がっていないということです。今日も「知っている」と答えてくれた方は半数ほどでした。ただ一方で、手話に興味を持ってくれる方が多かったのはとても嬉しかったです。
デフバドミントンの魅力は、速いラリーの駆け引きや、表情を読み合う心理戦にあります。私の強みについては、ダブルスではペアを組んでいる妹との息の合った連携、シングルスでは最後まで諦めない粘り強さだと思っています。
東京で開催されるデフリンピックについては、これをきっかけに障害に対する理解がもっと広がり、きこえない人も生きやすい社会につながっていってほしいと期待しています。私自身の目標は、女子ダブルスでの金メダル獲得です。4年に一度しかない舞台に立てることを誇りに、全力で挑みたいと思います。応援してくださる皆さんと一緒にデフリンピックを盛り上げていきたいです。

主催者コメント

デフリンピックの気運を醸成するため、デフアスリートによる講演を企画しました。あまり他に実施例がなく不安もありましたが、パラくる事務局の担当者が講師選定の際も希望を汲みつつとても親切に事業を進めてくれました。また、手話通訳を交えての打ち合わせや講演自体の段取りも経験が乏しく最初は不安でしたが、矢ケ部選手が大会を控えた時期にも関わらず非常に協力的で円滑にコミュニケーションをとっていただきました。その結果、講演は充実したすばらしい内容となり、参加者の関心も高く非常に好評であったと思います。
-
戻る









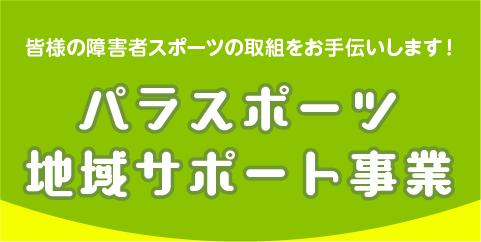




デフアスリートにとって、海外遠征時の栄養管理は大変!
矢ケ部選手は2002年生まれ、福岡県出身の24歳。小学1年生の時にろう学校でバドミントンに出会い、高校2年生で日本代表入りを果たしました。大学2年生でデフリンピック初出場を経験し、現在はアスリート雇用制度を活用しながら競技と仕事を両立しています。
講演は、矢ケ部選手自身の「聞こえ方」の説明から始まりました。補聴器を装着しても音がゆがんで聞こえるため理解が難しく、マスクなどで口元が見えないと相手の話していることが全くわからないといいます。幼少期に所属していたバドミントンクラブでは自分以外は皆聞こえる人だったので、監督やコーチの話がわからず孤立感を抱くこともあった一方、デフのバドミントンクラブでは手話通訳が入ることで内容がしっかりと理解でき、分かり合える仲間と安心して練習できたと振り返りました。
また、食と栄養についても学生たちに語りかけました。日頃から特に「疲れにくい体づくり」を意識し、1日3食を欠かさず、自炊では野菜をたっぷり取り入れているそうです。しかし、海外遠征では高カロリー・偏りがちな食事に悩み、体調を整えることに苦戦するといいます。現状、デフバドミントンには管理栄養士の帯同がなく、学生に向けて「学んでいる栄養の知識をスポーツの世界でも役立ててくれたら嬉しい」と伝えました。
デフリンピックの魅力については、視覚(目から入る情報)を活かした工夫を紹介。サッカーでは笛の代わりに旗を振り、陸上や水泳ではランプでスタートの合図を送ります。観客の応援も、拍手の代わりに「手をひらひらさせる動き」で表現されると説明。会場の学生たちも一緒に体験して盛り上がりました。加えて、矢ケ部選手から「※サインエール」の紹介とともに、「目に見える形で応援してもらえると、選手としてはとても嬉しい」と伝えました。
※サインエール・・・きこえる・きこえないにかかわらず、全ての人がデフアスリートに想いを届けることができるよう、目で世界を捉える人々の身体感覚と日本の手話言語をベースに創られた、新たな応援スタイル(デフアスリートに届ける新しい応援スタイル『サインエール』 | TOKYO FORWARD 2025)
講演会後半では、東京パラくる事務局のスタッフも登壇しトークショースタイルで矢ケ部選手に質問が投げかけられました。テーマは日常生活の工夫から競技への取り組みまで幅広く、会場は和やかな雰囲気と共感に包まれました。
最後の参加者からの質疑応答でも、「海外の選手とはどうやって意思疎通をしているの?」「試合前に緊張を和らげる方法は?」といった具体的な質問が次々と飛び出しました。矢ケ部選手は一つひとつに丁寧に答え、「手話や言葉が通じなくても表情やジェスチャーで伝え合える」「負けると思えば負けてしまう。勝つイメージを持って臨むことが大切」と、自身の経験を通じて学んだことを共有しました。