- 実施事例
- 日本代表選手も参加!東京都知的障がい者サッカー連盟による講演会
講演会事例 日本代表選手も参加!東京都知的障がい者サッカー連盟による講演会
- 主催者
- 小平市立上水中学校
- 講師
- 東京都知的障がい者サッカー連盟

- 開催日
-
- 2024.12.11(水)
- 場所
-
- 小平市立上水中学校 体育館
- 対象
-
- 全生徒
- 参加人数
-
- 約307名
見えづらい障害だからこそ、自ら積極的にコミュニケーションを取ってほしい

オリンピック・パラリンピック教育に取り組んでいる小平市立上水中学校では、関連イベントを継続的に開催しています。今回は担当教諭の元教え子が知的障がい者サッカーの日本代表とのご縁もあり、同選手も所属する東京都知的障がい者サッカー連盟から、木村純一コーチと選手5名に参加してもらい、講演会を実施しました。
まずは、日本に7つある障がい者サッカー(団体)の違いを説明しました。その後、車いすに乗っている人が駅で困っている状況と、友だちと上手に遊ぶことができないでいる子どもの様子を紹介。
ディスカッションタイムや発表の時間を設け、障害などで困っている人への接し方について、自ら考えるとともにまわりの人と考えを共有する時間を設けました。
車いすの事例では、障害は個人の心身機能によるものではなく、社会によって作り出されるものであるという考え方が世界全体の潮流であり、上水中の皆さんの回答からも、その考え方が浸透していることが感じられました。一方で、友達と上手に遊ぶことができない事例はどうでしょうか。こちらは障害があっても見えづからったり、わかりづらかったりするかもしれません。そういった障害であっても、その個人を原因とせず、周りの環境を調整することが大切だと、日本が2014年に締結した「障害者権利条約」の内容も紹介しながら説明され、その上で、差別があってはならないことも、伝えました。両者には障害があるといっても、「見えやすい/見えづらい障害」「わかりやすい/わかりづらい障害」という違いがあると木村さんは言います。そして、「まわりからはふつうにやっていると思われていた」「覚えるのが苦手」「先生の説明が一度ではわからない」など、選手たちが小さいころに困っていたことを、選手たち自らの言葉で伝えました。
見えづらい、わかりづらいから障害だからこそ、まわりにいるかも知れないと思いながら生活すること。見かけた際にはこちらから状況を気遣うと同時に、積極的にコミュニケーションを取ることが大事であることを話しました。
漢字ではなく、ひらがなで。言葉ではなく、動作や色などの視覚情報で。サッカーであれば蹴り方を教える際には実際に蹴って手本を見せるなど、適切なコミュニケーション方法も具体的に教えてくれました。
さらに、言葉でコミュニケーションを取る際には、短く簡単な内容で伝えること。かつ「いいね!」「一緒にやろう!」などポジティブな声がけをすること、改めてサッカーでのコミュニケーションを例に出し、「サッカーを通じて知的障害がある人もない人も、明るく楽しく元気よく、一緒にサッカーができる世界を目指しています」。
このようなメッセージで、講演会を締めました。


知的障害者への正しいイメージや接し方を理解する機会となった

教員
私自身、特別支援学級のある学校で勤務をする中で、障害のある生徒へのイメージが変わっていったことがありました。事前にアンケートを取ると、多くの生徒も以前の私のように偏見や誤ったイメージが散見されました。
講演を通じ、内容はもちろん、選手たちと直に接したことで、知的障害のある人へのイメージや接し方を理解する機会になったと、手応えを感じています。
東京パラくるは、いろいろな競技団体やパラアスリートの方たちとのネットワークをお持ちなので、今後イベントを開催する際もお願いしたいと考えています。
生徒
これまで実感がありませんでしたが、実は身近にいたかもしれない。また障害があってもサッカーを頑張っている選手の姿を見て、自分も頑張ろうと思いました。
-
戻る









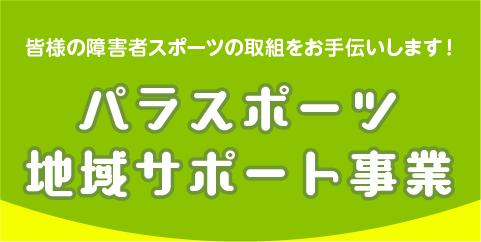




地域の中で障害があってもなくても助け合える土壌ができるとよい
イベント終了後は選手ならびに木村コーチ、主催者からメッセージをいただきました。
・選手2名
原選手:最初は緊張しましたが生徒の方から話しかけてくれたので、自然にうまくコミュニケーションが取れたと思います。大きな場で話すことで自分自身も成長できると感じています。
小川選手:自分がそうでしたが、知的障害者の中には思っていることを口に出すのが苦手なタイプが多いです。中学生であれば「勉強がわからない」などで、そのような言葉を気軽に発することのできる環境を構築してほしいと思います。
・木村コーチ
さすがは中学生。講演内容を熱心に聞いてくれるので、話しやすかったです。質問に関しても深く考えた上での内容で、充実した講演会になりました。
知的障害のことを知らないことが課題であり、知らないものには不安や恐怖といった心情がでてしまいます。まずは知ってもらうことが大切であり、私たちにとっては、その手段がサッカーだと考えています。自分たちはサッカーを通してコミュニケーションをとったり、一緒に仲間としてプレーすることで知ってもらおうと思っています。このような取り組みを行うことで、地域の中で障害があってもなくても助け合える土壌ができるとよい。このように思っています。